プロジェクトを円滑に進行するためには、プロジェクトの全体像を把握することが大切です。
プロジェクトの全体像を明確にし、確実に進捗管理するために役立つのが、作業工程表です。
工程表(作業工程表)に沿って工程管理をおこなえば効率的に業務をこなせるようになり、納期の遅延を防止できるでしょう。
その他にも、作業工程表の作成には工期の短縮やコスト削減など、さまざまな意味があります。
今回は、作業工程表の基礎知識や5種類の作業工程表の特徴、作り方などをわかりやすく解説します。
プロジェクトをスケジュールとおりに進められず、いつも納期に追われてしまう悩みを抱えている人はぜひ参考にしてみてください。
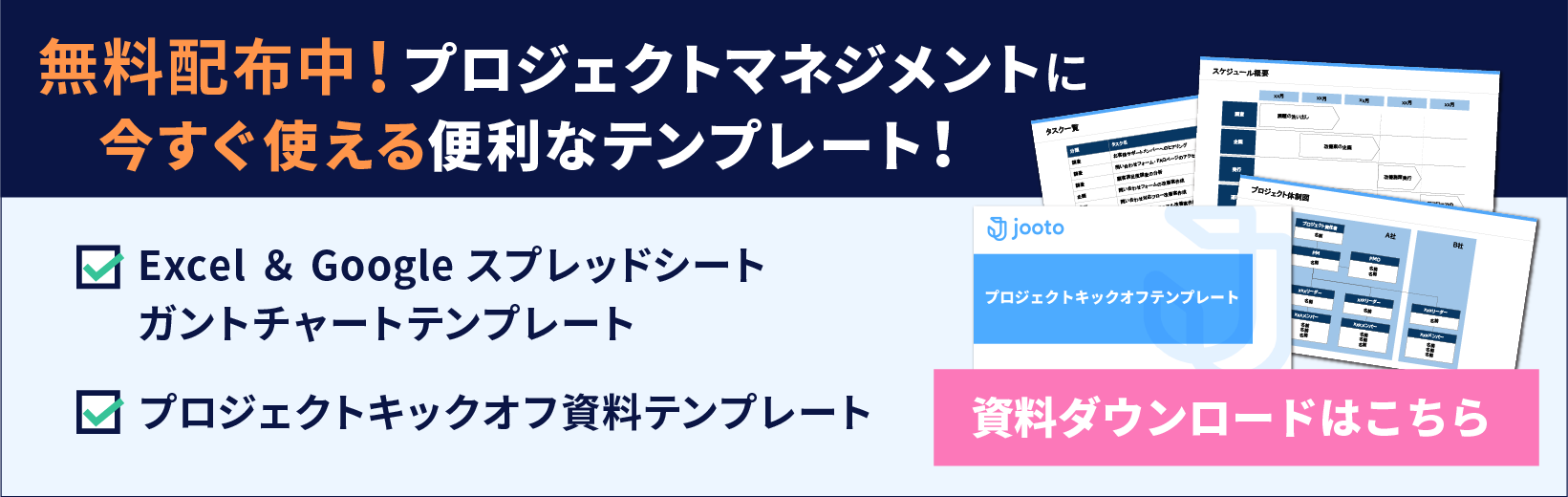
目次
工程表(作業業工程表)とは
工程表(作業工程表)とは、工期を守るためのスケジュール管理表です。
特に建設業界における工事現場などで、着工から完工までのスケジュールをまとめた施工管理表として用いられます。
建設業界において工程表は、原価管理や品質確保、発注管理にも活用される重要なものです。
建設業の現場作業を担う工務店の方針や施主の意向によっては工程表を用意しない場合があるかもしれませんが、工程表がないとスケジュールや人員管理を効率的におこなえず、業務効率が下がる恐れがあります。
また、施主とゴールや全体像を共有できないため、認識の齟齬が発生するリスクも高くなるでしょう。
工程表(作業工程表)は建設現場で用いられるだけでなく、プロジェクトのスケジュール管理ツールとしても有効です。
作業工程表というと、一般的には縦軸に作業を並べ、横軸にその作業を実施する日付を時系列で並べた施工管理表がイメージされますが、その他にもさまざまな種類があり、種類によってメリット・デメリットがあります。
行程表との違い
「工程表」とよく似た言葉に「行程表」がありますが違いはあるのでしょうか。
「工程表」と「行程表」は読み方が同じため混同されがちですが、別のものとして認識する必要があります。
「工程表」は建設業の現場でよく使われる言葉で、明確な目標やゴールに向けて具体的な手段や手順を示したものです。
これに対して「行程表」は、工程表よりも漠然とした予定や目標に対する手順や方法、大まかなスケジュールを記載します。
ロードマップと呼ぶこともあり、「工程表」と比較するとゴールに至るまでの手順に選択の余地があります。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
作業工程表の目的と役割
工程表(作業工程表)にはさまざまな目的と役割があり、具体的には以下のことに役立つと言われています。
- 納期を守る
- 工期の短縮
- コストの削減
- 作業効率の向上
- トラブルの回避、対処
それぞれについて詳しく解説します。
納期を守る
工程表(作業工程表)をもとに確実に工程管理することは、納期の遵守につながります。
作業工程表には、細かい工程や工数、スケジュールが記載されています。精度の高い作業工程表を作成すれば、工程管理・進捗状況の把握が容易になり、トラブルや遅れが生じたときにもすぐに現状を把握することが可能です。
作業工程表に沿ってプロジェクトを進めていくことで、計画通りの納期を実現できるのです。
工期の短縮
工程表(作業工程表)があることで、プロジェクト全体を俯瞰してみることができ、人員や材料を効率的に手配できるため、工期の短縮につながります。
作業工程表を作成する過程で、省いたり短縮したりできる工程が見えてくることもあるでしょう。
そして、配置する人員を増やすことで効率よく進められる工程や、逆に人員を割かなくても同等の成果が望める工程なども見えてきます。
それらを総合的に判断し、調整することで、工期の短縮につなげられるのです。
注意点としては、顧客の希望の納期が必ずしも正しいとは限らないことです。
顧客の要望をすべて聞き入れ、無理なスケジュールを組むと、結果としてミスや漏れが頻発したり、成果物のクオリティが低くなったりする事態もありえます。
無理なスケジュール設定を防ぐためにも、できるだけ細部まで記載された作業工程表を作成しましょう。
現実的なスケジュールを組むことで、顧客に対しても明確な根拠を示しながら納期や経費の説明ができます。
コストの削減

工程表(作業工程表)はコストの削減にも効果的です。
工程表に沿って作業を進めることで業務効率化を図ることができ、無駄な人件費などが省けるため、コストの削減につながります。
プロジェクトの計画段階で全体の工数の他、どの工程にどれくらいの時間と費用がかかるのか細かく計算することで、人員配置や機材・材料手配を効率よくおこなえます。
業務効率化の実現
工程表(作業工程表)の作成は、業務効率化にも寄与します。
作業工程表によって作業の進捗率が一目で把握できるため、作業が停滞している工程をいち早く知ることができ、対処できるようになります。
また、適切な人員配置や管理も実現するため、全体として作業効率が大幅に上昇するのです。
トラブルの回避、対処
工程表(作業工程表)を作成することで、トラブルの回避やイレギュラーな事態への対処ができるようになります。
スケジュールを詰めて組むのではなく、事前にトラブル発生を見越して作業工程表に空白期間を設けることがポイントです。
トラブルの発生で作業に遅れが生じても、空白期間で対処することが可能になります。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
工程表(作業工程表)の作成手順
工程表(作業工程表)にはさまざまな役割があることを解説しました。
作業工程表の具体的な作成手順は、以下の通りです。
- 施工手順を決める
- 施工期間を決める
- 施工期間に合わせて業務を配分する
- 工程表の種類を決める
それぞれについて詳しく解説します。
施工手順を決める
まずは適切な施工手順を決めます。
施工手順は、できるだけ細かく洗い出すことがポイントです。
作業内容が漠然としていてわかりにくいと、工程表自体がわかりにくく、現場で役立たないものになってしまいます。
特に重要な作業については、その部分だけピックアップして別に工程表を作成することもあります。
施工期間を決める
施工手順が明確になったら、施工期間を決めます。
業務の難易度や人的リソースを考慮して決めることがポイントです。
施工期間が短いと、常に作業に追われることになり、人的ミスが発生しやすくなります。
反対に長く設定し過ぎると、ムダな人件費が発生してしまうため、注意が必要です。
また、イレギュラーな事態が発生することに備えて、バッファを設けておくことも大切です。
一時的に作業がストップしても納期までにすべての作業を完了できるように設定しましょう。
施工期間に合わせて業務を配分する
施工期間が決まったら、業務を配分していきます。
納期までにすべてが完了するように、全体の進捗を考慮して工程の順番を調整することがポイントです。
機械や設備の使用が必要な作業がある場合は、使用予定日が重複しないように調整する必要があります。
トラブルが発生しても余裕をもって対処できるように、計画に柔軟性をもたせることが大切です。
工程表の種類を決める
最後に、工程表の種類を決めます。
工程表の作成方法は、施工順に進める「順行法」と納期から逆算して計画する「逆算法」の2種類が一般的です。
工程表の種類は複数ありますが、後述する5種類の工程表(作業工程表)のメリット・デメリットを考慮して目的に合ったものを選びましょう。
作成方法と種類が固まったら、ワードやエクセルなどを活用して工程表の作成を進めます。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
工程表(作業工程表)の種類
工程表(作業工程表)の種類は多岐に渡ります。
それぞれ特徴があるので、プロジェクトにとって最適なものを検討し導入してください。
便利に使い分けることも可能です。
Excelなどを使って作る場合は、テンプレートをダウンロードできるサイトもあるので、探してみるとよいでしょう。
主な工程表は、下記の5種類です。
- バーチャート工程表
- ガントチャート工程表
- グラフ式工程表(曲線式工程表)
- 工程管理曲線(出来高累計曲線)
- ネットワーク工程表
それぞれについて詳しく解説します。
バーチャート工程表

バーチャート工程表は、最もポピュラーな作業工程表の形式で、特に建設業界の施工管理に使用されることが多いことが特徴です。
縦軸に作業項目(タスク)、横軸に作業をおこなう日付を記入します。
作業の全体像や工程にかかる日数を視覚的に確認可能です。
バーチャートは、ガントチャートと呼ばれることもあります。
タスクと予定を記入するだけなので作成や修正が容易で、誰が見てもスケジュールが把握しやすい点がメリットですが、各タスク間の関連がわかりづらいというデメリットがあります。
そのため、作業の進捗管理には向いていません。
ガントチャート工程表

ガントチャート工程表はバーチャートに似ていますが、横軸に日付ではなく作業の進捗率を記入します。
横軸が予定日時から進捗率に変わっただけなので、作成や修正が簡単でスケジュールが見やすいというメリットはバーチャートと同じです。
各タスクをおこなう日付も記載すれば、進捗とスケジュールが一目でわかるようになり、スケジュール管理に役立ちます。
バーチャートと同様に各タスク間の関連性がわかりづらいというデメリットがあります。
グラフ式工程表(曲線式工程表)

グラフ式工程表は、バーチャートとガントチャートの特徴を併せ持ち、縦軸に進捗、横軸に日時を記入し曲線で進捗具合を表す工程表です。
作業間の依存関係が明確になるため、「どの作業が遅れると、どの作業に悪影響が出るのか」といった点がわかりやすくなります。
進捗率と作業予定日時の両方がわかるメリットがありますが、作成方法がバーチャートやガントチャートに比べてやや複雑なため、慣れるまでに時間がかかること、そしてタスク間の関連性がわかりづらい点がデメリットです。
工程管理曲線(出来高累計曲線)

工程管理曲線(出来高累計曲線)は、全体の進捗状況を把握するのに適した作業工程表です。
縦軸に進捗率(%)、横軸に日時を記入します。
工程管理曲線(出来高累計曲線)は、「バナナ曲線」や「Sカーブ」と呼ばれることもあります。
表の曲線を見れば、スケジュールがどのくらい遅れているのか一目で把握可能です。
上方・下方許容限界曲線を補助線として記入し、どこまで先行して進められるのか(上方)、どれだけ遅れても許容されるのか(下方)を確認できます。
全体の進捗を確認できるメリットがある一方で、各タスクの進捗を知ることができないというデメリットがあります。
ネットワーク工程表

ネットワーク工程表とは、円と矢印を利用し各タスクにかかる工数と各タスク間の全体像を示した作業工程表です。
矢印の上に作業名を記入し、矢印の下に作業日数を記載します。
主に、あるタスクが終わらないと次のタスクに移れないウォーターフォール型のタスクに用いられる工程表です。
例えばシステム開発の現場の場合、画面のデザインとデータベースの構築は同時に作業できますが、検索条件を入れて結果を出力する機能についてはデータベースの構築が終わらないと作業できません。
このような事例の場合は、ネットワーク工程表を用いると効果的にタスク管理できます。
メリットは、「最短でプロジェクトを終えるために同時に進められるタスクは何か」「どのタスクから着手したら効率がよいか」を把握できる点です。
しかし、作成するには専門的な知識が必要で難易度が高い点に注意が必要でしょう。
また、各作業の進捗がわかりづらいというデメリットがあります。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
バーチャート作業工程表が一般的
5つの工程表を紹介しましたが、一般的に用いられることが多いのはバーチャート・ガントチャートの工程表です。
バーチャート・ガントチャートの工程表は手書きで作成したり、ExcelやGoogleスプレッドシートで作成したりできます。
タスク・プロジェクト管理ツールである「Jooto」のガントチャート機能を利用すれば、より容易に作成できるでしょう。
エクセルでのバーチャートにはテンプレートが便利
表計算ソフトのエクセルは工程表の作業以外でも使用する機会が多く、従業員が使い慣れているツールです。
費用をかけることなく、手軽に工程表を作成できます。
関数やグラフなどを用いてカスタマイズできる点や、マクロを組んで自動化できるところがメリットです。
インターネットで検索すると、多くのエクセルテンプレートが提供されています。
エクセルテンプレートをうまく活用すれば、罫線の設定や数式の入力などの手間が省けます。
無料でダウンロードできるものも多いので、自社にあったものを選ぶとよいでしょう。
しかし、エクセルで作った工程表には、情報共有にタイムラグがあることや、個人によって体裁がバラバラになることが多く、属人化しやすいというデメリットがあります。
また、関数やマクロに関する知識がない人が運用に携わると、修正の際に数式が崩れることがあり、仕事に悪影響を及ぼす恐れがある点もデメリットでしょう。
外部の人と情報共有する際はパスワードをかけてメールに添付して送付する必要があり、手間がかかることも認識しておく必要があります。
エクセルでバーチャート作業工程表(一般的にいうガントチャート)を作成する方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。
同様に、Googleスプレッドシートを利用してバーチャート作業工程表を作成することもできます。
Googleスプレッドシートでの作成方法は以下の記事にてご確認ください。
ツールを使った作業工程表の作成がおすすめ
Excelやスプレッドシートを使ったバーチャート・ガントチャートの作成は、手間がかかります。
また、各タスクの担当者に進捗状況をその都度確認してから入力しなければならず、リアルタイムでの情報更新が困難です。
リアルタイムで情報が更新されないと確認作業が必要になったり、抜けや漏れ、遅れなどが生じる事態になったりと、工程表のメリットを活かせなくなります。
そこでおすすめなのが、ツールの導入です。
ガントチャート機能に優れたクラウドツールを使うことで、リアルタイムに進捗を確認できるようになります。
メンバーそれぞれが抱えるタスクの進捗状況を個々に入力すればよいため、報告などの手間もなくなり、管理者の負担を減らす効果もあります。
また、工程に必要なファイルなどの情報を一元管理できることも魅力です。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
Jootoを使って進捗管理を効率化しよう

クラウド型タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」なら、ガントチャートの作成がとにかく簡単!
エクセルやGoogleスプレッドシートのように、列や行の設定や入力の手順はまったく必要ありません。
Jootoはドラッグ&ドロップを基本操作とし、誰でも直感的・視覚的に使えるシンプルなデザインと操作性が魅力です。
カンバンボード内にタスクを登録し、日付や担当者を選択するだけで複雑な操作は必要ありません。
登録したタスクを付箋のように貼ったり剥がしたりしてリスト管理します。
タスクごとにチャットやファイル共有も可能で、必要な情報をすぐに取り出せる点もうれしいポイントです。
カンバンボードを見るだけで、進行中の案件内容や担当者が一目で把握できるので、管理時間の短縮に役立ちます。
また、登録したタスク情報から、ワンクリックでガントチャートが自動的に作成されます。
タスクの進捗を入力すれば、すぐさまガントチャートに反映されるため、プロジェクトのリアルタイムな進捗状況を、いつでも・どこでも・誰でも確認可能です。
ガントチャートにより、自分以外のメンバーのタスク量や進捗が可視化されるため、仕事量の偏りを防ぎ、効率よく人員を配置できます。
現場の進捗管理を効率化したい人は、ぜひJootoをチェックしてみてください。

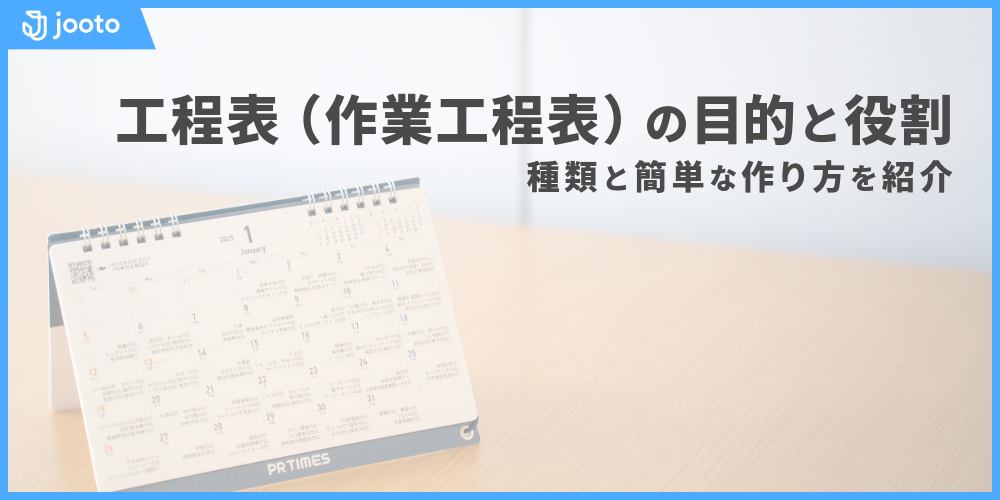

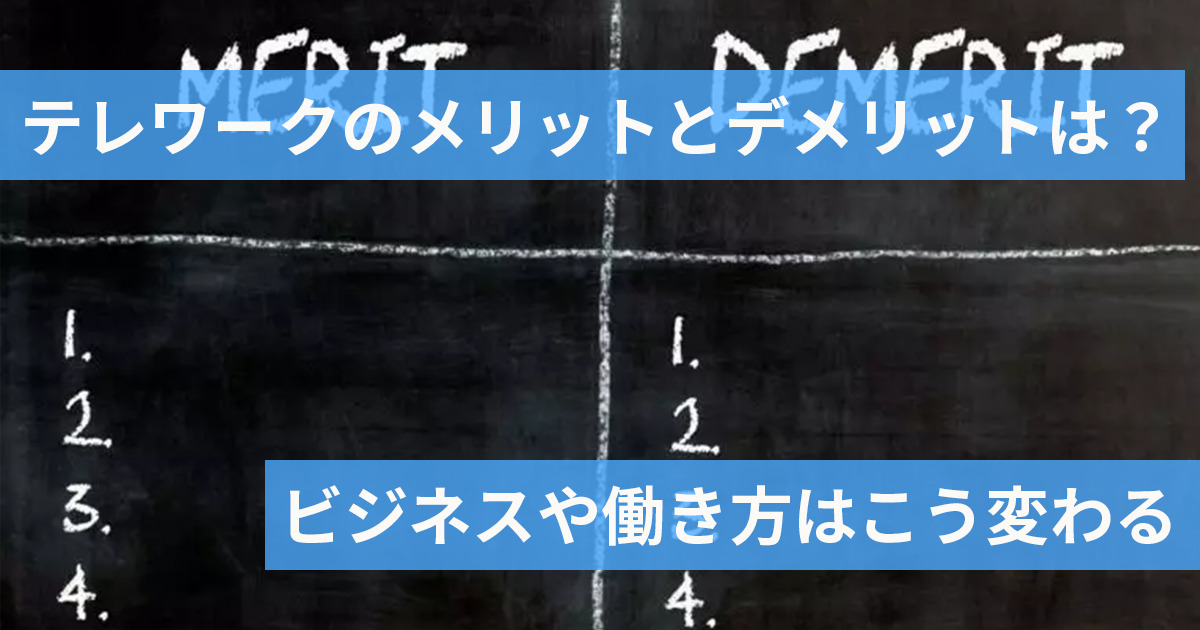
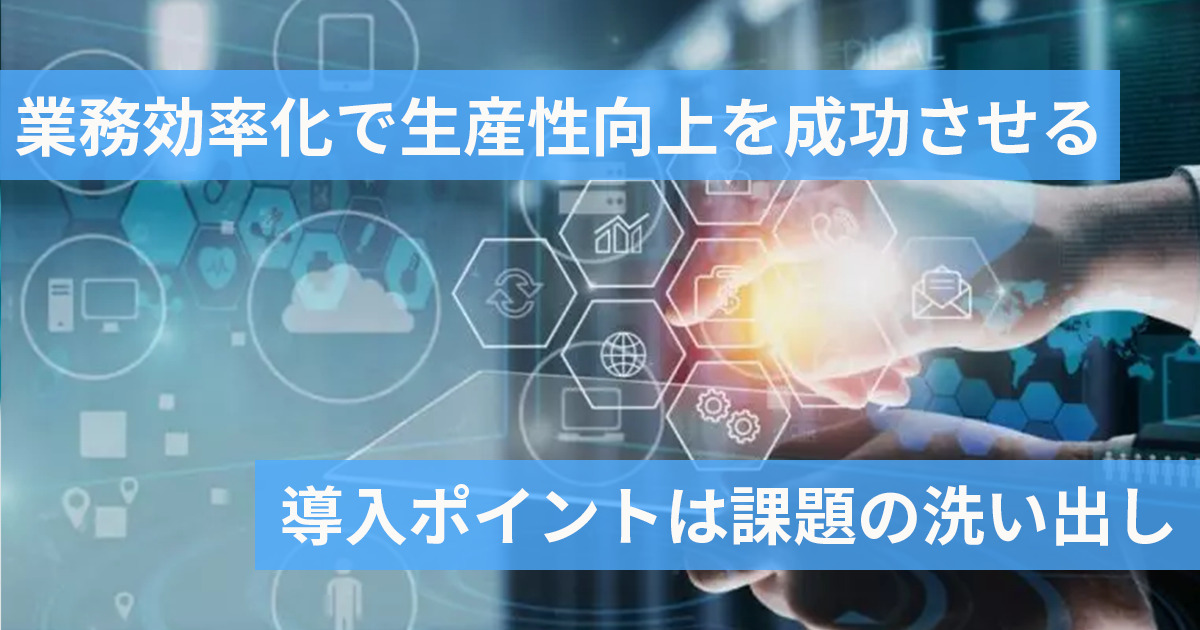
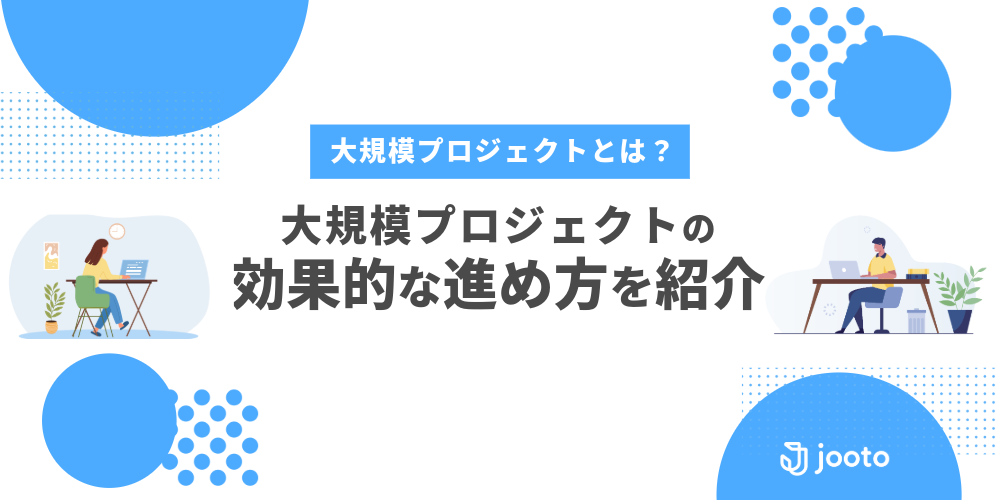

 © 2024 Jooto
© 2024 Jooto
Comments are closed.